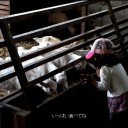プランターのいろどり1-紫陽花1
2016年6月18日 エッセイ
梅雨に紫陽花はつきもの、しっとりした情緒は他の花ではでてこない。
ユキノシタ科の落葉低木で良く繁茂し形は存在感の膨らみがある。本来の花は小さいのが特徴、通常花とみられているのはほとんど装飾花の集合体と思ったほうがいい。
日本古来の植物の一種であること、ナリ&イロ相からすると中国原産などとおもうがそうではない、単純に喜ばしいことではないかと、思った。
ユキノシタ科の落葉低木で良く繁茂し形は存在感の膨らみがある。本来の花は小さいのが特徴、通常花とみられているのはほとんど装飾花の集合体と思ったほうがいい。
日本古来の植物の一種であること、ナリ&イロ相からすると中国原産などとおもうがそうではない、単純に喜ばしいことではないかと、思った。
吉井川のいろどり6-閘門6-灌漑運河3
2016年6月14日 エッセイ
光政から綱政にバトンがわたった延宝の年早々、水害がたてつづけて発生した。20年前に挫折した干拓事業案のときは、光政の側小姓であった津田永忠は、藩財政の苦衷を身に沁みて感じていただろうから、新田開発すなわち米増産以外の方策はないと信じ、実地検分をやりなおして提言書を綱政に上程した。秀逸な内容は水源の課題を克服していたことだった。
結果として津田永忠が成した功績は先に廃案になった課題を 解決した。
①灌漑水路として吉井川吉井から旭川平井まで総延長20キロの運河を開拓すること。
②取水口は閘門を構築し水流を調整、併せて高瀬通しで物資交流の便宜を図ること。
この閘門運河の完成で藩の体質は好転したのはいうまでもない。
*画像 上&中 倉安川からみた第二水門
下 第二水門外の水留めに泳ぐ錦鯉
結果として津田永忠が成した功績は先に廃案になった課題を 解決した。
①灌漑水路として吉井川吉井から旭川平井まで総延長20キロの運河を開拓すること。
②取水口は閘門を構築し水流を調整、併せて高瀬通しで物資交流の便宜を図ること。
この閘門運河の完成で藩の体質は好転したのはいうまでもない。
*画像 上&中 倉安川からみた第二水門
下 第二水門外の水留めに泳ぐ錦鯉
吉井川のいろどり5ー閘門5-灌漑運河2
2016年6月13日 エッセイ
水難はいつの時代でも災害をもたらした。
氾濫した洪水が家屋田畑を呑みこむと生活そのものを破壊した。中世から江戸時代にわたり岡山は河川の災害が顕著だった。特に、宇喜多家が豊臣秀吉の助言により旭川の流れを城の防護のため城下につけかえたことによる氾濫時の水害は甚大なもので、住民は困窮きわまり、岡山藩は池田初期慢性化した赤字財政に苦しんだ。当時の流通経済は米づくりが基盤でなりたち米の欠乏はたちまち窮乏をもたらした。
可及速やかな対策は米の増産しかない。三代藩主池田光政は新田開発に着眼、旭川河口の平井から吉井川河口の金岡あたりまで新田開発が可能かどうか、明暦3(1657)年役人に調査を命じている。このあたりは両川河口の広い州浜(干潟)だった。役人の提出した干拓絵図をみた綱吉は、新田開発にもっとも必要とされる水源確保に目途がたたずにあるため、この事業案をやむなく断念している。
*画像 吉井川河畔
ガードレールのあるところが右岸で閘門ー倉安川の吉井水 門。今はコンクリートで改修封鎖されていて吉井川側にはその痕跡はなくなっている。右にこんこりした杜がみえるのが福岡城跡。左の街郭は備前長船町。
氾濫した洪水が家屋田畑を呑みこむと生活そのものを破壊した。中世から江戸時代にわたり岡山は河川の災害が顕著だった。特に、宇喜多家が豊臣秀吉の助言により旭川の流れを城の防護のため城下につけかえたことによる氾濫時の水害は甚大なもので、住民は困窮きわまり、岡山藩は池田初期慢性化した赤字財政に苦しんだ。当時の流通経済は米づくりが基盤でなりたち米の欠乏はたちまち窮乏をもたらした。
可及速やかな対策は米の増産しかない。三代藩主池田光政は新田開発に着眼、旭川河口の平井から吉井川河口の金岡あたりまで新田開発が可能かどうか、明暦3(1657)年役人に調査を命じている。このあたりは両川河口の広い州浜(干潟)だった。役人の提出した干拓絵図をみた綱吉は、新田開発にもっとも必要とされる水源確保に目途がたたずにあるため、この事業案をやむなく断念している。
*画像 吉井川河畔
ガードレールのあるところが右岸で閘門ー倉安川の吉井水 門。今はコンクリートで改修封鎖されていて吉井川側にはその痕跡はなくなっている。右にこんこりした杜がみえるのが福岡城跡。左の街郭は備前長船町。
吉井川のいろどり4-閘門4-灌漑運河
2016年6月7日 エッセイ
吉井水門閘門は、高瀬舟など用船の便と共に灌漑を図ることが重要な目的で、江戸初期の光政、綱政ー熊沢蕃山、津田永忠の苦闘のドラマにつながっていくけれど、つぶさな経緯は短文には描ききれない。洪水災害は承応、延宝年間に幾度も勃発し岡山城下はもちろん備前平野に氾濫して多くは水没、家屋田畑、住民に惨憺たる被害をもたらした。
吉井川のいろどり3-閘門3
2016年6月6日 エッセイ
「閘門」(こうもん)とは平常使わない言葉で、門構えのなかに甲があるので広辞林でひくと、[(運河などで)船を高低差の大きい水面に航行させるため、水位を調整する装置の水門]と書かれていた。
ここでいうと、取水する吉井川の水位が高く放流する倉安川が低いので、吉井川の堤防を掘削して第一水門をつくり内側に第二水門を構築、第一と第二の間には船溜まり(高瀬廻し)を設けている。吉井川からの高瀬舟は第一水門を開くことで水量とともに船溜まりに入って、ついで第一水門は閉め、船溜まりで船の方向調整、通行税の徴収手続きをおこなったのち、第二水門を除除に開けて放水し受手の倉安川と同等の水位まで下げ船を通過させる、逆の場合は上記の手順が反対になる。また洪水時の氾濫を避けた退避場所にもなった。船の運航の便をまかなうばかりではなく灌漑に大きく貢献した。こういった方式は古代中国に多くあったようで、近くはパナマ運河にも採用されている。
第二水門の上に番小屋があって船溜まりの南側にある石段の上には番所屋敷があり、水門や側面のそれらを支える石垣は野面積みでありながら備前積みの頑強さと美しさを今にのこしている。
着工は1679年(延宝7)の2月、完成したのが同年8月といわれているから、当時の工作としては短期間の完成である。
ここでいうと、取水する吉井川の水位が高く放流する倉安川が低いので、吉井川の堤防を掘削して第一水門をつくり内側に第二水門を構築、第一と第二の間には船溜まり(高瀬廻し)を設けている。吉井川からの高瀬舟は第一水門を開くことで水量とともに船溜まりに入って、ついで第一水門は閉め、船溜まりで船の方向調整、通行税の徴収手続きをおこなったのち、第二水門を除除に開けて放水し受手の倉安川と同等の水位まで下げ船を通過させる、逆の場合は上記の手順が反対になる。また洪水時の氾濫を避けた退避場所にもなった。船の運航の便をまかなうばかりではなく灌漑に大きく貢献した。こういった方式は古代中国に多くあったようで、近くはパナマ運河にも採用されている。
第二水門の上に番小屋があって船溜まりの南側にある石段の上には番所屋敷があり、水門や側面のそれらを支える石垣は野面積みでありながら備前積みの頑強さと美しさを今にのこしている。
着工は1679年(延宝7)の2月、完成したのが同年8月といわれているから、当時の工作としては短期間の完成である。
吉井川のいろどり2-閘門2
2016年6月4日 エッセイ
資料をめくると、江戸が一大消費都市で栄えたのは高瀬舟の便が発達していたからという一文がある。
趣意は栃木の鬼怒川上流から利根川へ帆船(高瀬舟)が行き交い江戸の街へ生活物資をはこびこんで需要をうるおした、ということであろう。あらためて、河川と人間との関りあいは飲水のみあらず都市形成の基盤を支えていたことを認識するのである。
高瀬舟が発達し活躍したのは江戸時代になるが、発祥したのは室町時代までさかのぼるようだ。このころは長距離運送までいかなくて、ごく近辺の用を達してこと足れりであっただろうが、そのうち河口のデルタ地帯に人口が集結し需要が勃発すれば比例して十分な供給の便を構築しなけねばならず、おのずから改良の高瀬舟を運行させたのであろう。
吉井川、旭川、高梁川の岡山三大河川も御多聞にもれず中世から高瀬舟が煩多に往来して物資を供給していた。河川の流れ川幅など現代の川相とは比較できないほど原始で不整備であったろうことは想像にかたくない。ことに風眉には富んでいるものの奇岩巨石が川面にのぞく高梁川は中流域まで白波たてて岩を噛む渓流相で、さぞかし難多く舟材に工作がいっただろうと想うし、比較的ゆったり蛇行する旭川、吉井川にしても相応の苦行があったことは想うにむずかしくない。
運行の遺跡として旭川は勝山、吉井川は津山に発着場の痕跡がのこっている。さらに本流を支流として曳き込んで運河をつくり高瀬舟を誘導、供給の効率化をはかるばかりか原野を開墾開拓して肥沃な耕作地に転じさせ豊穣をもたらす事業を興すことにもなった。そこで生じた水位の差を操作する施工技術が必要になってくる。
「閘門」という調整施設を可能したのが池田光政・綱政ー津田永忠の施政者ー奉行のラインだ。
今もその施設が吉井川に現存している。
趣意は栃木の鬼怒川上流から利根川へ帆船(高瀬舟)が行き交い江戸の街へ生活物資をはこびこんで需要をうるおした、ということであろう。あらためて、河川と人間との関りあいは飲水のみあらず都市形成の基盤を支えていたことを認識するのである。
高瀬舟が発達し活躍したのは江戸時代になるが、発祥したのは室町時代までさかのぼるようだ。このころは長距離運送までいかなくて、ごく近辺の用を達してこと足れりであっただろうが、そのうち河口のデルタ地帯に人口が集結し需要が勃発すれば比例して十分な供給の便を構築しなけねばならず、おのずから改良の高瀬舟を運行させたのであろう。
吉井川、旭川、高梁川の岡山三大河川も御多聞にもれず中世から高瀬舟が煩多に往来して物資を供給していた。河川の流れ川幅など現代の川相とは比較できないほど原始で不整備であったろうことは想像にかたくない。ことに風眉には富んでいるものの奇岩巨石が川面にのぞく高梁川は中流域まで白波たてて岩を噛む渓流相で、さぞかし難多く舟材に工作がいっただろうと想うし、比較的ゆったり蛇行する旭川、吉井川にしても相応の苦行があったことは想うにむずかしくない。
運行の遺跡として旭川は勝山、吉井川は津山に発着場の痕跡がのこっている。さらに本流を支流として曳き込んで運河をつくり高瀬舟を誘導、供給の効率化をはかるばかりか原野を開墾開拓して肥沃な耕作地に転じさせ豊穣をもたらす事業を興すことにもなった。そこで生じた水位の差を操作する施工技術が必要になってくる。
「閘門」という調整施設を可能したのが池田光政・綱政ー津田永忠の施政者ー奉行のラインだ。
今もその施設が吉井川に現存している。
吉井川のいろどり1-閘門1-高瀬舟
2016年6月2日 エッセイ
はじめに 「閘門」の読みは見てのごとし「こうもん」で、意味あいは後頁に述べます。
古来、山側と海側の物資交流は欠かせざる生活循環でありつづけ文化発展の起点でもあった。現在でもその原則は無変である。
米麦野菜などの食材、良質木材、砂鉄等鉄鉱石を下流域へ、下流域からは塩、海産物、衣類、雑貨加工品などの物資を上流域へ廻送して流通させた。運送手段で、先ず想いつくのが人力、ついで牛馬となるがそれでも荷役量となると多寡がしれている。ある程度の積荷を確保して長距離輸送をまかなうのには、川上から下流まで一途通じている河川の利用がもっとも効率的であることに着眼したのは当然だったろう。
舟そのものも川相に適うように改良を重ね、今は記念品として保存展示されている舟形に終結になった。したがってそれぞれの適合は川相にあわして若干ちがうにしろ、長さ20メートル横幅3メートル内外、深さ0.7メートルが標準で、底は波を切るより川床の岩石を噛まないように平底に工夫した。米勘定して250~500俵は積載できたようだ。錦絵などをみると上舟に曳き綱をつけた上り舟には両岸の大勢の人足が依ってひっぱっているし、時には牛を使って牽引しているのをみると重労働だったようだ。
船頭はじめ4~5人で操船した。
古来、山側と海側の物資交流は欠かせざる生活循環でありつづけ文化発展の起点でもあった。現在でもその原則は無変である。
米麦野菜などの食材、良質木材、砂鉄等鉄鉱石を下流域へ、下流域からは塩、海産物、衣類、雑貨加工品などの物資を上流域へ廻送して流通させた。運送手段で、先ず想いつくのが人力、ついで牛馬となるがそれでも荷役量となると多寡がしれている。ある程度の積荷を確保して長距離輸送をまかなうのには、川上から下流まで一途通じている河川の利用がもっとも効率的であることに着眼したのは当然だったろう。
舟そのものも川相に適うように改良を重ね、今は記念品として保存展示されている舟形に終結になった。したがってそれぞれの適合は川相にあわして若干ちがうにしろ、長さ20メートル横幅3メートル内外、深さ0.7メートルが標準で、底は波を切るより川床の岩石を噛まないように平底に工夫した。米勘定して250~500俵は積載できたようだ。錦絵などをみると上舟に曳き綱をつけた上り舟には両岸の大勢の人足が依ってひっぱっているし、時には牛を使って牽引しているのをみると重労働だったようだ。
船頭はじめ4~5人で操船した。
里山のいろどり16-山羊牧場3
2016年5月28日 趣味里山のいろどり15-山羊牧場2
2016年5月24日 エッセイ
広葉落葉樹の色あいが日ごと濃さを増す新葉を、キラキラ射る陽光が透過して人や大地にまだら模様を映しだす。風にゆれると、幻影のように輪郭をぼかして揺れ騒ぎ、陽炎でもたちそうな初夏の昼下がりである。
山羊乳をのんで、それのソフトクリームを舐め、ブランコやハンモックであそび、くたびれて眠る、孫娘のその様子は得心のいった寝顔であった。
山羊乳をのんで、それのソフトクリームを舐め、ブランコやハンモックであそび、くたびれて眠る、孫娘のその様子は得心のいった寝顔であった。
里山のいろどり14-山羊牧場1
2016年5月23日 エッセイ
上道の山間に忽然とあらわれる山羊牧場、はじめて出かける人は枝分かれした細道に戸惑うかも知れない。しかし知る人は知るところだろう、子ずれ孫ずれで賑わっていた。生きた動物と間近に接するのは広い意味で情緒教育になる。
かって戦後の農家では、一頭飼っていて山羊乳は貴重な乳製品として扱われていた。母乳の代替品としては秀逸の養分をふくみ、子供の育成に貢献してきた。
かって戦後の農家では、一頭飼っていて山羊乳は貴重な乳製品として扱われていた。母乳の代替品としては秀逸の養分をふくみ、子供の育成に貢献してきた。
百閒川のいろどり48ー愛犬天国1
2016年5月22日 ペット
河川敷きのペット散歩はほどよい運動だ。
排泄処理の袋を携えおやつの小袋をもって、ちょっと遠歩きの目標で歩くと、十分体をほぐすことはできる。
真冬と真夏のときは時間帯をかんがえないと後悔することがある。冬は一番気温があがる午どき夏は落日の夕暮れどきがいいのだが、緑地公園なので河川敷きに降りる道のゲートが19時で閉鎖される。
画像はMさんの撮影:投稿
排泄処理の袋を携えおやつの小袋をもって、ちょっと遠歩きの目標で歩くと、十分体をほぐすことはできる。
真冬と真夏のときは時間帯をかんがえないと後悔することがある。冬は一番気温があがる午どき夏は落日の夕暮れどきがいいのだが、緑地公園なので河川敷きに降りる道のゲートが19時で閉鎖される。
画像はMさんの撮影:投稿
里山のいろどり13-里山センター2
2016年5月17日 エッセイ
詩人室井犀星の有名な詩。
ふるさとは遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの よしや うらぶれて異土の乞食と なるとても 帰るところにあるまじや ひとり都のゆふぐれに ふるさとおもひ涙ぐむ その こころもて 遠きみやこにかへらばや ・・・
[小景異情ーその二] より
単に望郷の想いを述べたものではなくて、作家志望の初志を果たせなく苦悶して、東京と金沢を幾度なく往復していたときの詩作である。
溢れる思索に悶々するのは少年期の特有のもので今昔を問わない、空想や想像、憧れが今おもえばおかしいほど先行して多くは挫折をあじわいながら現実の社会に巻きこまれていき、それから幾年経て、うろこが剥がれ解き放されてできたゆとりと伴に、田舎風自然に触れなごみ少年期のよすがを見いだして綿を絞るように昔日の日々を滲ませては想い枯れていくものなのである。
犀星の世界と少々異なるけれど、原風景へ繋がる糸は現代と同じだろうと想う。
画像上:”柿のつの” 沢田は富有柿の産地、たわわに稔る秋 には河川敷きで盛大な柿祭りがおこなわれる。農家が培う 柿の木は操山の彼方此方の斜面を覆い、剪定をかさねた 梢はトナカイの角のように伸びて屈し目をみはる。
画像中:炭焼き小屋 体験学習の施設。竹炭の材料が積まれ ている。
画像下:歌碑2基
ふるさとは遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの よしや うらぶれて異土の乞食と なるとても 帰るところにあるまじや ひとり都のゆふぐれに ふるさとおもひ涙ぐむ その こころもて 遠きみやこにかへらばや ・・・
[小景異情ーその二] より
単に望郷の想いを述べたものではなくて、作家志望の初志を果たせなく苦悶して、東京と金沢を幾度なく往復していたときの詩作である。
溢れる思索に悶々するのは少年期の特有のもので今昔を問わない、空想や想像、憧れが今おもえばおかしいほど先行して多くは挫折をあじわいながら現実の社会に巻きこまれていき、それから幾年経て、うろこが剥がれ解き放されてできたゆとりと伴に、田舎風自然に触れなごみ少年期のよすがを見いだして綿を絞るように昔日の日々を滲ませては想い枯れていくものなのである。
犀星の世界と少々異なるけれど、原風景へ繋がる糸は現代と同じだろうと想う。
画像上:”柿のつの” 沢田は富有柿の産地、たわわに稔る秋 には河川敷きで盛大な柿祭りがおこなわれる。農家が培う 柿の木は操山の彼方此方の斜面を覆い、剪定をかさねた 梢はトナカイの角のように伸びて屈し目をみはる。
画像中:炭焼き小屋 体験学習の施設。竹炭の材料が積まれ ている。
画像下:歌碑2基
里山のいろどり12ー里山センター1
2016年5月16日 エッセイ
一定の年齢にはいりこむと、郊外の自然裡に足をすすめていたら、時として故郷の風景が脳裏を足早に通りすぎるのを、あれっと自覚することがある。現実に見ている描写に少年期の想いがラップして、その頃の風景と似通うのである。想いは留まらずに泡沫のように消えてしまい、なんの繋がりがあるのだろうかと思考するのだが、単に故郷のある匂いや開がりがたまさかそこに湧き出ていたからで、特段の望郷や懐古に浸っていた訳ではない。日本の原風景といわれるような現実にであったら、DNAに刷りこまれた少年期の光景が頭に点滅したのだろう。
百閒川の堤防道路を沢田の里山センターへの径は、まさしくそういったスクリーンである。
画像上:竹の秋 幹も葉も紅葉のように黄味を帯びてい て、季語では今の時期の竹を「竹の秋」という。筍に養分を注ぎ窶れた現象である。
中:ため池の小径1 集落にむかって建つ祠
下:ため池の小径2 バードウオッチングに良好
百閒川の堤防道路を沢田の里山センターへの径は、まさしくそういったスクリーンである。
画像上:竹の秋 幹も葉も紅葉のように黄味を帯びてい て、季語では今の時期の竹を「竹の秋」という。筍に養分を注ぎ窶れた現象である。
中:ため池の小径1 集落にむかって建つ祠
下:ため池の小径2 バードウオッチングに良好
里山のいろどり9-小手毬
2016年5月9日 エッセイ
虫明・黒井山牡丹園
花名には殆ど和名がついていて、色、形、葉、茎などの特質を冠せて、その言い当て妙な意味に感嘆し、納得するものが少なくない。このコデマリもそうだ、膝をたたいて思わず叩頭したくなるほど適性をつかんでいる。
古い時代に中国から渡来したようで、かの国の前世における自然のもたらした壮大な文化や雅趣、それに心琴をかたむけた詩人のあしあとがしのばれる。
五弁を散形花状にまとめて丸くなり、稚げの掌に可愛く載るのは正しく毬である。
別名スズカケはどこからきたものだろうか、ちなみに修験者が首に懸ける衣の輪宝に似ているからという説がある。
個人的には小豆島寒霞渓の急峻な崖に多くの白い花がつらなって咲いていたのが、あれがコデマリだったけ、の憶いが内包されていて、ある時おもいつきに植木市で苗を調達、鉢植えしたものが毎年咲き、今年も真っ白に飾りはや散った。
(画像はクリックしてご覧ください)
花名には殆ど和名がついていて、色、形、葉、茎などの特質を冠せて、その言い当て妙な意味に感嘆し、納得するものが少なくない。このコデマリもそうだ、膝をたたいて思わず叩頭したくなるほど適性をつかんでいる。
古い時代に中国から渡来したようで、かの国の前世における自然のもたらした壮大な文化や雅趣、それに心琴をかたむけた詩人のあしあとがしのばれる。
五弁を散形花状にまとめて丸くなり、稚げの掌に可愛く載るのは正しく毬である。
別名スズカケはどこからきたものだろうか、ちなみに修験者が首に懸ける衣の輪宝に似ているからという説がある。
個人的には小豆島寒霞渓の急峻な崖に多くの白い花がつらなって咲いていたのが、あれがコデマリだったけ、の憶いが内包されていて、ある時おもいつきに植木市で苗を調達、鉢植えしたものが毎年咲き、今年も真っ白に飾りはや散った。
(画像はクリックしてご覧ください)
里山のいろどり8ー牡丹8
2016年5月7日 エッセイ
虫明・黒井山牡丹園
イエロー
山田洋次監督の映画「幸せの黄色いハンカチ」をおもいだす。
この色の底辺には抑制のなかでの淡い思い、秘められた想いを内包している。
同じ東備のやや北になるが、穂浪地域では純文学の正宗白鳥 剣豪小説の柴田練三郎を輩出している。
(画像はクリックしてご覧ください)
イエロー
山田洋次監督の映画「幸せの黄色いハンカチ」をおもいだす。
この色の底辺には抑制のなかでの淡い思い、秘められた想いを内包している。
同じ東備のやや北になるが、穂浪地域では純文学の正宗白鳥 剣豪小説の柴田練三郎を輩出している。
(画像はクリックしてご覧ください)
里山のいろどり7-牡丹7
2016年5月6日 エッセイ
虫明・黒井山牡丹園
ホワイト
純潔、無垢という言葉が 先ず浮かぶ。色彩がなくて何色にも染まるのが特性で、旧くから花嫁衣装は純白が定番であるのもこれのながれ、といわれる。嫁ぐ家になじみ夫の色に染まり、幸せになるという意味がこめられているそうだが、はたしてそうだろうか、新郎の白いタキシードは、長い伴侶の末にいたっては汚れに汚れ、立場が逆転して妻の色に染められて身動きできなくなっている己にはっと気がつく、こんな現象が多いのでは。団塊世代を謳歌した者への挽歌だ。
「白牡丹と いふといへども 紅ほのか」 (高浜虚子)
「白牡丹 李白が 顔に崩れけり」 (夏目漱石)
(画像はクリックしてご覧ください)
ホワイト
純潔、無垢という言葉が 先ず浮かぶ。色彩がなくて何色にも染まるのが特性で、旧くから花嫁衣装は純白が定番であるのもこれのながれ、といわれる。嫁ぐ家になじみ夫の色に染まり、幸せになるという意味がこめられているそうだが、はたしてそうだろうか、新郎の白いタキシードは、長い伴侶の末にいたっては汚れに汚れ、立場が逆転して妻の色に染められて身動きできなくなっている己にはっと気がつく、こんな現象が多いのでは。団塊世代を謳歌した者への挽歌だ。
「白牡丹と いふといへども 紅ほのか」 (高浜虚子)
「白牡丹 李白が 顔に崩れけり」 (夏目漱石)
(画像はクリックしてご覧ください)
里山のいろどり5ー牡丹5
2016年5月3日 エッセイ
虫明・黒井山牡丹園
ピンク 2
絵心ある人なら一度は牡丹を描いてみたいおもうだろう。
色ならずとも波形の花弁の連なり重なりを具象化してみたいおもいにかられ、絵筆を走りさせたい衝動をおこさせることはないだろうか。単に同じピンク色ではなく、濃淡、陰影、映えを使い分けて能動的な趣を表現させることができたらと、絵心ない者が敢えて願望するのである。
海側の麓は虫明地区であり、温暖な風土は平安時代から詩に詠まれ歴史をきざんでいる。また、岡山池田藩筆頭家老伊木家の在所として栄え、明治をむかえている。
(画像はクリックしてご覧ください)
ピンク 2
絵心ある人なら一度は牡丹を描いてみたいおもうだろう。
色ならずとも波形の花弁の連なり重なりを具象化してみたいおもいにかられ、絵筆を走りさせたい衝動をおこさせることはないだろうか。単に同じピンク色ではなく、濃淡、陰影、映えを使い分けて能動的な趣を表現させることができたらと、絵心ない者が敢えて願望するのである。
海側の麓は虫明地区であり、温暖な風土は平安時代から詩に詠まれ歴史をきざんでいる。また、岡山池田藩筆頭家老伊木家の在所として栄え、明治をむかえている。
(画像はクリックしてご覧ください)