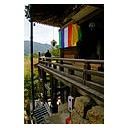林がさながら丸坊主のように伐採された。
中州がなくなり緑の楽園風景が消滅されてしまった。
水鳥の遊弋と野鳥の飛翔がみえなくなり、囀りさえ途絶えてしまった。
対岸のビル群がまるみえでとびこんでくる。
太陽と風の遊園地が出来た。
百閒川への放流地を少し下った旭川左岸の河川敷きの景観だ。
画像上:解放観の修復後景観 夕暮
画像下:放恣に咲くノコンギク
中州がなくなり緑の楽園風景が消滅されてしまった。
水鳥の遊弋と野鳥の飛翔がみえなくなり、囀りさえ途絶えてしまった。
対岸のビル群がまるみえでとびこんでくる。
太陽と風の遊園地が出来た。
百閒川への放流地を少し下った旭川左岸の河川敷きの景観だ。
画像上:解放観の修復後景観 夕暮
画像下:放恣に咲くノコンギク
休日で晴天であれば観光客の賑わいは沸騰している。
ただ気温が30度超えると、館内をくまなく見て回る気力体力が萎えてしまい、アイスクリームやかき氷の売店に殺到して長い行列ができる。また、動こうとしない。イルカの人気ショウの脇にある水槽までたどりつき、枯れ木に団子のように絡みあってなにがなんだか良く分からず、それがコンダと認識して目を合わせ、「ギョ」とした。
いやな動物は寒気たつので、腰がひける、ならば水槽に近づかねばいいのだが、怖いものみたさの性分でおまけに老眼となればメガネを外して水槽にはりつく姿勢になり、瞬きしない冷徹な目、長い胴に鱗が生え攻撃のさい相手をぐるぐる巻いて窒息せしめるまで離れない生態の恐ろしさを認識して、後ずさりした。そして。前節の驚愕、「ぞ~っ」と怖気
に襲われた。
イルカショウを観る気にもなれなくて、早々に館外へのがれた。巳の年にして、巳がもっとも嫌いなのである。
画像上中:水族館正面入り口
画像下:?意識せずに写した画像、あとで見たら横眼で 睨まれていた・・・!!
ただ気温が30度超えると、館内をくまなく見て回る気力体力が萎えてしまい、アイスクリームやかき氷の売店に殺到して長い行列ができる。また、動こうとしない。イルカの人気ショウの脇にある水槽までたどりつき、枯れ木に団子のように絡みあってなにがなんだか良く分からず、それがコンダと認識して目を合わせ、「ギョ」とした。
いやな動物は寒気たつので、腰がひける、ならば水槽に近づかねばいいのだが、怖いものみたさの性分でおまけに老眼となればメガネを外して水槽にはりつく姿勢になり、瞬きしない冷徹な目、長い胴に鱗が生え攻撃のさい相手をぐるぐる巻いて窒息せしめるまで離れない生態の恐ろしさを認識して、後ずさりした。そして。前節の驚愕、「ぞ~っ」と怖気
に襲われた。
イルカショウを観る気にもなれなくて、早々に館外へのがれた。巳の年にして、巳がもっとも嫌いなのである。
画像上中:水族館正面入り口
画像下:?意識せずに写した画像、あとで見たら横眼で 睨まれていた・・・!!
魅惑な舞いークラゲー須磨海浜水族館-1
2017年10月19日 エッセイ
夏の濁りは下流にうつり、澄み切った水中の小魚はナイフの刀身のように鱗をひらめかせて藻と遊ぶ。山稜のブナ林に降った雨水は地中に蓄えられ永い年月をかけて山麓に湧出し、渓谷を幾筋も集めて下り河川なり網の目のような用水を経て人間の生活を潤しているのだ。
古寺素描55-薬師寺⑥(完)ー鐘楼・東塔
2017年10月1日 エッセイ
食堂伽藍を出ていくと東側の広場に鐘楼がある。これを観てびっくりした。
各寺院を徘徊していて大抵何らかの伽藍とか門、あるいは樹木の陰、高台になった処などに吊られサビワビを晒すがごとくに建立されているのを観てきた。寂陰を一身に背負い立つ伽藍にどこにもある安穏をおぼえるのだ。謂れある銘を刻したした名鐘も普段は脇役であるが夕映えの平野になり渡るとき、晦日に殷賑と音が凍てつくときにはとてつもない主役の存在になる。
ところが薬師寺の鐘楼は平地(薬師寺の伽藍はすべて平地建立)にあって、しかも四面あっけらんかんと開放されている。それはそれなりに史実を想像するが自分の未詳ゆえこれ以上のことはない。
ただし周囲をハスの鉢植えに囲まれ仰ぎ見られている。
塔は本来お釈迦様のお墓だ。もともと梵語の「ストゥーパ」が卒塔婆[そとうば]となり、それが塔婆、更には塔と表現され、お釈迦様のご遺骨(仏舎利[ぶっしゃり])を埋葬して盛り土をしたものが。その塔婆を遠くからでも拝めるように、台上にお祀りしたのが三重塔、五重塔のはじまりだ。
薬師寺東塔は一見六重に見えるが、実は三重の塔、西塔と同じだ。各層に裳階[もこし]と言われる小さい屋根があるためで、この大小の屋根の重なりが律動的な美しさをみせている。
薬師寺で唯一創建当時より現存している建物で、1300年の時を重ねてきた歴史の美しさである。解体修理のため残念ながら、現在は覆屋に覆われておりその姿をみることができない。(平成32年の6月頃に修理完成予定)。
画像上:鐘楼
画像下:修復工事前の東塔
各寺院を徘徊していて大抵何らかの伽藍とか門、あるいは樹木の陰、高台になった処などに吊られサビワビを晒すがごとくに建立されているのを観てきた。寂陰を一身に背負い立つ伽藍にどこにもある安穏をおぼえるのだ。謂れある銘を刻したした名鐘も普段は脇役であるが夕映えの平野になり渡るとき、晦日に殷賑と音が凍てつくときにはとてつもない主役の存在になる。
ところが薬師寺の鐘楼は平地(薬師寺の伽藍はすべて平地建立)にあって、しかも四面あっけらんかんと開放されている。それはそれなりに史実を想像するが自分の未詳ゆえこれ以上のことはない。
ただし周囲をハスの鉢植えに囲まれ仰ぎ見られている。
塔は本来お釈迦様のお墓だ。もともと梵語の「ストゥーパ」が卒塔婆[そとうば]となり、それが塔婆、更には塔と表現され、お釈迦様のご遺骨(仏舎利[ぶっしゃり])を埋葬して盛り土をしたものが。その塔婆を遠くからでも拝めるように、台上にお祀りしたのが三重塔、五重塔のはじまりだ。
薬師寺東塔は一見六重に見えるが、実は三重の塔、西塔と同じだ。各層に裳階[もこし]と言われる小さい屋根があるためで、この大小の屋根の重なりが律動的な美しさをみせている。
薬師寺で唯一創建当時より現存している建物で、1300年の時を重ねてきた歴史の美しさである。解体修理のため残念ながら、現在は覆屋に覆われておりその姿をみることができない。(平成32年の6月頃に修理完成予定)。
画像上:鐘楼
画像下:修復工事前の東塔
古寺素描54ー薬師寺⑤ー食堂
2017年9月26日 エッセイ
金堂の奥に大講堂があり、さらに奥に食堂が建っている。
丹に彩られた艶やかな伽藍で、これまで幾度も火災に遭って焼失していて、創建当初の建物は天平2年(730)頃に建立、天禄4年(973)に焼失しその後、寛弘2年(1005)に再建されている。その規模は東大寺、大安寺につぐものだといわれていて、僧侶約300人が一堂に介して斎食できるそうである。
特別内部公開で入室できてみて、なるほど広いと感じる、本尊「阿弥陀三尊浄土図」を中心に50メートルにわたる壁画「仏教伝来の道と薬師寺」が奉納され、雰囲気からして一般のわれわれが食事をする気分には、とてもなれない。
僧侶の食事のほか多目的行事にも使用されているようだ。
画像上:食堂入り口
画像下:食堂全景
丹に彩られた艶やかな伽藍で、これまで幾度も火災に遭って焼失していて、創建当初の建物は天平2年(730)頃に建立、天禄4年(973)に焼失しその後、寛弘2年(1005)に再建されている。その規模は東大寺、大安寺につぐものだといわれていて、僧侶約300人が一堂に介して斎食できるそうである。
特別内部公開で入室できてみて、なるほど広いと感じる、本尊「阿弥陀三尊浄土図」を中心に50メートルにわたる壁画「仏教伝来の道と薬師寺」が奉納され、雰囲気からして一般のわれわれが食事をする気分には、とてもなれない。
僧侶の食事のほか多目的行事にも使用されているようだ。
画像上:食堂入り口
画像下:食堂全景
古寺素描53-薬師寺④-金堂「本堂」
2017年9月17日 エッセイ
本尊を安置している伽藍を本堂というのが一番身近だが、仏殿とか金堂とか別称の言葉で敬うのが古都の地では多い。いかにも華やかで尊厳のひびきをするが、やはり本堂といったほうが古めかしく落ちつきがあるような気がする。されど、別の価値感で解釈するとなると、金ぴかでしかも巨仏であればあるほど、かててくわえて権利権威の謂れがあればこそ金堂といったほうが言葉の響きと求心力をあつめて民を驚愕させ、ゆるぎない信仰を集めるるのに相応しいのかもしれない。宗教も人間の性を引きずっているからであろう。
大門くぐって直線上に本堂があり、その奥に塔があるのが宗派によっては決められた配置になっているが、ここ薬師寺では金堂の東西に仏舎利を祀る二基の塔が脇を固めて建っている。詳細はわからないが珍しい配置である。
享禄元年(1528)この地域の豪族・筒井順興の戦火に巻きこまれ、西塔などと共に焼け落ちた。その後、豊臣家が金堂の仮堂を建て、その後本格的な金堂の再建に取りかかる筈だったが、豊臣家滅亡などの事情で400年近く仮堂のままであった。金堂の再建は歴代の薬師寺住職にとって悲願を伝え昭和42年(1967)高田好胤師が晋山し、百万巻写経勧進による金堂再建を提唱、全国に写経勧進に歩き、その結果昭和46年(1971)金堂の起工式を行い、そして昭和51年(1976)4月に白鳳時代様式の本格的な金堂として復興している。
大門くぐって直線上に本堂があり、その奥に塔があるのが宗派によっては決められた配置になっているが、ここ薬師寺では金堂の東西に仏舎利を祀る二基の塔が脇を固めて建っている。詳細はわからないが珍しい配置である。
享禄元年(1528)この地域の豪族・筒井順興の戦火に巻きこまれ、西塔などと共に焼け落ちた。その後、豊臣家が金堂の仮堂を建て、その後本格的な金堂の再建に取りかかる筈だったが、豊臣家滅亡などの事情で400年近く仮堂のままであった。金堂の再建は歴代の薬師寺住職にとって悲願を伝え昭和42年(1967)高田好胤師が晋山し、百万巻写経勧進による金堂再建を提唱、全国に写経勧進に歩き、その結果昭和46年(1971)金堂の起工式を行い、そして昭和51年(1976)4月に白鳳時代様式の本格的な金堂として復興している。
古寺素描52-薬師寺③-三重塔・西塔
2017年9月11日 エッセイ
南門を経て中門をくぐるといきなり華麗な色彩の建物が目にとびこんでくる。正面に金堂、西手に三重塔がおもいきり迫ってくる。三重の屋根の下に小さい屋根がついているので六重塔に見える。薬師寺特有の形式をもつ東西二つ塔の、これは西塔である。
あおによし ならのみやこは さくははなの におうがごとく いまさかりなり
万葉集にうたわれた薬師寺の一節である。「あお」と「丹に」に彩られ、白壁の連子窓と相まって平城京の華やかさが
風に舞って降りかかってくる。
正面の金堂と、右手の東塔とは回廊でつながっている。
画像上下:西塔
拡大画像は画像をクリックしてください。
あおによし ならのみやこは さくははなの におうがごとく いまさかりなり
万葉集にうたわれた薬師寺の一節である。「あお」と「丹に」に彩られ、白壁の連子窓と相まって平城京の華やかさが
風に舞って降りかかってくる。
正面の金堂と、右手の東塔とは回廊でつながっている。
画像上下:西塔
拡大画像は画像をクリックしてください。
古寺素描51-薬師寺②-平城京・奈良
2017年9月7日 エッセイ
宗派は法相宗、同じ法相宗で朝廷に深く入り込んだ興福寺と並び、薬師寺は特定の檀家組織を持たないが、宗派の二大総本山となっている。宗派の教義は難解で知識未熟ではとても理解できない。一時代、管長の高田好胤師(故人)が伽藍再興の勧進でTVなどの説話でやさしく説いていたが根本はむつかしい。
1300年前の白鳳時代、時の皇后(のちの持統天皇)の病気平癒を祈願して藤原京に創建したのが始まりで持統天皇を経て文武天皇の代に飛鳥の地にて堂宇が完成、さらに平城遷都(718・養老2年)で現在地に移されている。移転については、伽藍、仏像を全部そのまま移したという説と、寺院の名籍だけを移し伽藍や仏像は新しく造立したという論争が平成の今に続いている。前説なら東塔や薬師三尊像などは白鳳時代の作となり、後説では天平初期の作となるため、美術史学界を二分する重大な問題であろう。なにせ古代のできごとで蜜な記録や痕跡のないのが、学者や小説家の想像をかきたててやまないのである。
金堂、講堂などを中心に、東塔と西塔の2つの三重塔を配する構成は独特なもので、薬師寺式伽藍配置と呼ばれていまる。この華麗な伽藍も数次の火災にあって次々と焼失し、創建当時の姿を残すのは東塔のみ。しかし、昭和51年(1976)金堂が、昭和56年(1981)には西塔が、その後中門、回廊、玄奘三蔵院伽藍が復原造営され、平成15年(2003)には大講堂も落慶し、今なお白鳳伽藍の復興を目指して再建中だ。
画像上:金堂 西塔 東塔が描かれている。背景に若草山 の丘陵もある。
画像中:薬師三尊
画像下:本尊 薬師如来
1300年前の白鳳時代、時の皇后(のちの持統天皇)の病気平癒を祈願して藤原京に創建したのが始まりで持統天皇を経て文武天皇の代に飛鳥の地にて堂宇が完成、さらに平城遷都(718・養老2年)で現在地に移されている。移転については、伽藍、仏像を全部そのまま移したという説と、寺院の名籍だけを移し伽藍や仏像は新しく造立したという論争が平成の今に続いている。前説なら東塔や薬師三尊像などは白鳳時代の作となり、後説では天平初期の作となるため、美術史学界を二分する重大な問題であろう。なにせ古代のできごとで蜜な記録や痕跡のないのが、学者や小説家の想像をかきたててやまないのである。
金堂、講堂などを中心に、東塔と西塔の2つの三重塔を配する構成は独特なもので、薬師寺式伽藍配置と呼ばれていまる。この華麗な伽藍も数次の火災にあって次々と焼失し、創建当時の姿を残すのは東塔のみ。しかし、昭和51年(1976)金堂が、昭和56年(1981)には西塔が、その後中門、回廊、玄奘三蔵院伽藍が復原造営され、平成15年(2003)には大講堂も落慶し、今なお白鳳伽藍の復興を目指して再建中だ。
画像上:金堂 西塔 東塔が描かれている。背景に若草山 の丘陵もある。
画像中:薬師三尊
画像下:本尊 薬師如来
古寺素描50-薬師寺①-平城京・奈良
2017年9月4日 エッセイ
7月の有日、大和路の著名古刹に足を踏み入れた。
薬師寺は広大な敷地に規模の大きい伽藍を配した古刹、謂れの多い寺歴をあわせて、じっくり観察するだけで相当の時間を要する。とうり抜け程度では歩みを停めるわけにはいかない。圧巻だけで終わりになるのである。
画像上:画像3枚とも南門へ至る路から。工事中の東塔遠望
画像中:石畳の路
画像下:西塔遠望
薬師寺は広大な敷地に規模の大きい伽藍を配した古刹、謂れの多い寺歴をあわせて、じっくり観察するだけで相当の時間を要する。とうり抜け程度では歩みを停めるわけにはいかない。圧巻だけで終わりになるのである。
画像上:画像3枚とも南門へ至る路から。工事中の東塔遠望
画像中:石畳の路
画像下:西塔遠望
古寺素描49-笠場山普門寺(完)ー花の山寺・真庭市
2017年8月17日 エッセイ
前記のがくあじさいを元に品種改良を重ねて、今庭園や公園に植栽している各種のあじさいを齎した。寺社にあじさいを冠した観光名所が多くなったのは其れ以降。
ぼんぼんに似た大きな花は派手で見栄えするが、立ち止まってしみじみ眺めるには時として胃もたれしないでもない。屈んで覗き見るのが好きな者は、豊満な大形美人に圧倒され蒸せる思いがする。
画像上:屋外の椅子で愛犬と戯れる
画像中:広い径が狭くなる
画像下:がくあじさい
画像拡大は画像をクリックしてください
ぼんぼんに似た大きな花は派手で見栄えするが、立ち止まってしみじみ眺めるには時として胃もたれしないでもない。屈んで覗き見るのが好きな者は、豊満な大形美人に圧倒され蒸せる思いがする。
画像上:屋外の椅子で愛犬と戯れる
画像中:広い径が狭くなる
画像下:がくあじさい
画像拡大は画像をクリックしてください
古寺素描48ー笠場山普門寺④ー花の山寺・真庭市
2017年8月16日 エッセイ
普門寺あじさい景色①
緑をこいで歩いていると沢沿いのあじさいに出会うことが、夏時期に多い。がくあじさいである。中央に小さい花片をびっしり集めた散房花序をつけ、その周囲に大きな装飾花があるのが特徴である。
拡大画像は画像をクリックしてください。
緑をこいで歩いていると沢沿いのあじさいに出会うことが、夏時期に多い。がくあじさいである。中央に小さい花片をびっしり集めた散房花序をつけ、その周囲に大きな装飾花があるのが特徴である。
拡大画像は画像をクリックしてください。
古寺素描47-笠場山普門寺③-花の山寺・真庭市
2017年8月14日 エッセイ
寺院は816年に弘法大師によって開かれたと言われる非常に長い歴史がある。伽藍そのものは歴史に合致して風格ある装いをみせている。
客殿の縁側に腰をおろして面前にひらける枯山水の庭を眺めていると、自我を忘れ、時の移ろいを費やす樂世の感がある。
ついつい童謡を口ずさむ世界である。
もっとも当寺は若い和尚さんのような気がするが。
山寺の和尚さんが
毬はけりたし 毬はなし
猫をかん袋に 押し込んで
ポンとけりゃ ニャンとなく
ニャンがニャンとなく ヨイヨイ
山寺の狸さん
太鼓打ちたし 太鼓なし
そこでお腹を チョイと出して
ポンと打ちゃ ポンと鳴る
ポンがポンと鳴る ヨイヨイ
画像上:客殿
画像中:枯山水庭園
画像下:山門 鐘楼
拡大画像は画像をクリックしてください
客殿の縁側に腰をおろして面前にひらける枯山水の庭を眺めていると、自我を忘れ、時の移ろいを費やす樂世の感がある。
ついつい童謡を口ずさむ世界である。
もっとも当寺は若い和尚さんのような気がするが。
山寺の和尚さんが
毬はけりたし 毬はなし
猫をかん袋に 押し込んで
ポンとけりゃ ニャンとなく
ニャンがニャンとなく ヨイヨイ
山寺の狸さん
太鼓打ちたし 太鼓なし
そこでお腹を チョイと出して
ポンと打ちゃ ポンと鳴る
ポンがポンと鳴る ヨイヨイ
画像上:客殿
画像中:枯山水庭園
画像下:山門 鐘楼
拡大画像は画像をクリックしてください
古寺素描46-笠場山普門寺②-花の山寺・真庭市
2017年8月12日 エッセイ
普門寺の名を冠したお寺は、全国版でパラパラめくってみるだけで、ざっと10指を超える末寺があり、さらに天台宗、真言宗、曹洞宗・・・と各宗派に存在している。
字面がいいのと、音読みのながれが実に澱みなく素にして抗もないのが良いではないか。
真庭の普門寺は「花寺」としても近隣にことのほか評判だ。 春は「あじさい祭り」が有名で凡そ3000株30種類が境内はじめ門前に植栽され身丈ほど爛漫に咲くのは見事で、花と彩に酔って田舎蕎麦を啜るのは妙味である。
県下の「あじさい寺」の一つ。
因みに「四季桜」は春秋に咲き、秋の紅葉とのコントラストは絵筆やペンをはしらせてみたい衝動を覚える。
境内の短い石段を登ると門の内外に大きなタヌキの置物を飾っている。寺とタヌキに、なにか逸話でもあるのだろうか。おどけた表情に例の豊かな持物を署気の風にさらしていた。
塀沿いに行くと山門、仁王、鐘楼、本堂に行くので本来はこちらを辿るのだろうが、大方は石段から誘われるまま境内に自然と足を踏みいることになる。
画像上:門前
画像中:外塀の山門に辿る路
画像下:境内内庭
拡大画像は画像をクリックしてください
字面がいいのと、音読みのながれが実に澱みなく素にして抗もないのが良いではないか。
真庭の普門寺は「花寺」としても近隣にことのほか評判だ。 春は「あじさい祭り」が有名で凡そ3000株30種類が境内はじめ門前に植栽され身丈ほど爛漫に咲くのは見事で、花と彩に酔って田舎蕎麦を啜るのは妙味である。
県下の「あじさい寺」の一つ。
因みに「四季桜」は春秋に咲き、秋の紅葉とのコントラストは絵筆やペンをはしらせてみたい衝動を覚える。
境内の短い石段を登ると門の内外に大きなタヌキの置物を飾っている。寺とタヌキに、なにか逸話でもあるのだろうか。おどけた表情に例の豊かな持物を署気の風にさらしていた。
塀沿いに行くと山門、仁王、鐘楼、本堂に行くので本来はこちらを辿るのだろうが、大方は石段から誘われるまま境内に自然と足を踏みいることになる。
画像上:門前
画像中:外塀の山門に辿る路
画像下:境内内庭
拡大画像は画像をクリックしてください
古寺素描45ー笠場山普門寺①ー花の山寺・真庭市
2017年8月10日 エッセイ
奥深い山の頂上にある山寺、高野山真言宗で信奉信者が多いのかよく管理行き届いた門前、境内、伽藍、そして署気払いに客殿の園側に座って息を整えれば枯山水の庭は禅宗の庭によくみられる砂の掃目が斬新にかかれている。
門前に茶屋がならび近隣の女性が新鮮野菜や雑貨物、お餅や蕎麦などを商う屋台庇が出て食事ができるようになっている。しかし、聞き忘れたがいつも開いてはいないようで、多い催事に合わせて出店している趣である。当日も「あじさい祭り」の余韻を漂わして、さながら平安時代の市場を窺うようであった。
画像上:門前
画像中:門前石碑
画像下:境内に入る玄関口
拡大画像は画像をクリックしてください
門前に茶屋がならび近隣の女性が新鮮野菜や雑貨物、お餅や蕎麦などを商う屋台庇が出て食事ができるようになっている。しかし、聞き忘れたがいつも開いてはいないようで、多い催事に合わせて出店している趣である。当日も「あじさい祭り」の余韻を漂わして、さながら平安時代の市場を窺うようであった。
画像上:門前
画像中:門前石碑
画像下:境内に入る玄関口
拡大画像は画像をクリックしてください
古寺素描44-豊山長谷寺(完)-奈良
2017年8月4日 エッセイ
本堂を後にして大国堂、弘法大師御影堂、本長谷寺、経堂を横目でうかがいながら疲労ぎみの脚をなだめ先へ急ぐ。
大寺に付きものが三重塔・五重塔で、どちらかというと重厚な伽藍をみて抑えつけられるような気持ちに充ちていたところに天を貫くような塔に接すると、鬱積を吐きだす解放感を得られる。長谷寺の五重塔は艶やかな朱塗りでその彩色が緑陰によく映えていた。明治9年に落雷で焼失、昭和29年に建立された。完全、木造建築である。
塔の各層には仏教的宇宙観がこめられていて、下から地(基礎)、水(塔身)、火(笠)、風(請花)、空(宝珠)からなるもので、それぞれが5つの世界(五大思想)を示している。
仏教の祖である釈迦の舎利(遺骨)をおさめる仏塔の形式の一種で同種のものに三重塔などがある。
日本にいくつの三重塔、五重塔があろうか、釈迦佛の求心力を、人間社会は多として建立してきた。
それはともかく、伽藍を巡る僧侶の脚に疲れはないのだろうか。
大寺に付きものが三重塔・五重塔で、どちらかというと重厚な伽藍をみて抑えつけられるような気持ちに充ちていたところに天を貫くような塔に接すると、鬱積を吐きだす解放感を得られる。長谷寺の五重塔は艶やかな朱塗りでその彩色が緑陰によく映えていた。明治9年に落雷で焼失、昭和29年に建立された。完全、木造建築である。
塔の各層には仏教的宇宙観がこめられていて、下から地(基礎)、水(塔身)、火(笠)、風(請花)、空(宝珠)からなるもので、それぞれが5つの世界(五大思想)を示している。
仏教の祖である釈迦の舎利(遺骨)をおさめる仏塔の形式の一種で同種のものに三重塔などがある。
日本にいくつの三重塔、五重塔があろうか、釈迦佛の求心力を、人間社会は多として建立してきた。
それはともかく、伽藍を巡る僧侶の脚に疲れはないのだろうか。
古寺素描42-豊山長谷寺④-奈良
2017年8月3日 エッセイ
本堂は本瓦葺きの壮大な入母屋造り、創建以来、幾度も焼失復興をくりかえし、現在のものは徳川家光の寄進によって慶安3年に再建されたもの。細長い通路状の拝所を隔てた礼堂からなる双堂形式の複合仏堂である。荘厳な趣が空間に垂れこめている。
礼堂の正面は懸造りの広い舞台になっていて、京都清水寺に似て、その庇に立って眺めていると久しく歩をとどめておきたい感慨になる。
画像上:礼堂から五重塔の眺望
画像中:礼堂から西方の眺望
画像拡大は画像をクリックしてください
礼堂の正面は懸造りの広い舞台になっていて、京都清水寺に似て、その庇に立って眺めていると久しく歩をとどめておきたい感慨になる。
画像上:礼堂から五重塔の眺望
画像中:礼堂から西方の眺望
画像拡大は画像をクリックしてください
古寺素描41-豊山長谷寺③-奈良
2017年7月31日 エッセイ
山麓から中腹にかけて伽藍が広がる。入口の仁王門から本堂までは399段の登廊(のぼりろう)を上る。下登廊右手の傾斜には牡丹が咲きそろい(花の寺)と呼ばれる由縁である。登りつめるとV字型に岐路になり右の中登廊をとると、鐘楼経て上登廊にいたり豪壮な装飾で目を瞠るほどの本堂・礼堂があらわれる。
山麓から中腹にかけて伽藍が広がる。本堂の西方の丘には「本長谷寺」と称する一画があり、五重塔などが建つ。本堂が国宝に、仁王門、登廊5棟(下登廊、繋屋、中登廊、蔵王堂、上登廊)、三百余社、鐘楼、繋廊が重要文化財に指定されている。外部からいきなり暗部のなかにとびこみ、目が馴れていないのでなにがなにやらよくわからない。頭上の梁にぶつけながら目から散る灯りで前に進む、右が本堂、左が礼堂の配置で、その中央を善男善女が通る。カメラ禁止は当然、暗闇の燈明はなにやら朧で本尊の拝顔がかなわぬ道理である。
画像上:登廊の岐路 直進が上登廊下、右が中登廊、鐘楼
画像中:下登廊脇の牡丹園
画像下:右本堂 左礼堂
山麓から中腹にかけて伽藍が広がる。本堂の西方の丘には「本長谷寺」と称する一画があり、五重塔などが建つ。本堂が国宝に、仁王門、登廊5棟(下登廊、繋屋、中登廊、蔵王堂、上登廊)、三百余社、鐘楼、繋廊が重要文化財に指定されている。外部からいきなり暗部のなかにとびこみ、目が馴れていないのでなにがなにやらよくわからない。頭上の梁にぶつけながら目から散る灯りで前に進む、右が本堂、左が礼堂の配置で、その中央を善男善女が通る。カメラ禁止は当然、暗闇の燈明はなにやら朧で本尊の拝顔がかなわぬ道理である。
画像上:登廊の岐路 直進が上登廊下、右が中登廊、鐘楼
画像中:下登廊脇の牡丹園
画像下:右本堂 左礼堂
古寺素描40-豊山長谷寺②ー奈良
2017年7月28日 エッセイ
創建から室町時代まで7回も焼失している。
本尊の十一面観音は天正7年に再興されているが、本堂の再建は天正16年豊臣秀長が着手するまでは空白というのが謎といえば謎である。江戸時代、徳川家光の寄進があって三度の本堂落慶がおこなわれ、今の姿に続いている。すべからず現在の建物は、創建以来からの重厚な歴史にあわづ災害の繰り返しや社会事情によって江戸、明治以降のもので比較的浅い。
境内の正面に回廊の石段がのびている。屋根で覆っているから多少涼しげに思えるが傾斜はきつい。
画像上:案内図板
画像下:下登廊
本尊の十一面観音は天正7年に再興されているが、本堂の再建は天正16年豊臣秀長が着手するまでは空白というのが謎といえば謎である。江戸時代、徳川家光の寄進があって三度の本堂落慶がおこなわれ、今の姿に続いている。すべからず現在の建物は、創建以来からの重厚な歴史にあわづ災害の繰り返しや社会事情によって江戸、明治以降のもので比較的浅い。
境内の正面に回廊の石段がのびている。屋根で覆っているから多少涼しげに思えるが傾斜はきつい。
画像上:案内図板
画像下:下登廊