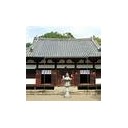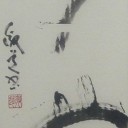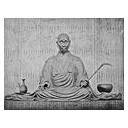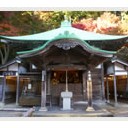古寺探訪67ー中宮寺ー奈良
2018年5月24日 エッセイ
聖徳太子といえば飛鳥時代の偉人で国の基を成す条項を数々制定した人、というのが我々の知識に刷りこまれている。細かい資料をみていると、伝説にまつわることも散見していて、この人はイエス・キリストに近似したようなところがあると想うのだがいかがかであろうか。
もっとも、身近の印象がするのはやはり一万円札を崇拝してやまないからだろうか。
中宮寺は聖徳太子の母、穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇后の菩提を弔うために宮を寺にしたものである。法隆寺に所在する聖徳宗の寺院で、山号を法興山といい、開基は聖徳太子であるが、創建の詳細な事情は不明となっている。
金堂は、昭和43年建立の鉄筋コンクリート造り、境内に佇むと尼寺特有の清楚さが流れる。
拡大画像は画像をクリックしてください。
画像上:金堂
画像下:木造菩薩半跏像(国宝)
(平成30年3月8日 探訪)
もっとも、身近の印象がするのはやはり一万円札を崇拝してやまないからだろうか。
中宮寺は聖徳太子の母、穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇后の菩提を弔うために宮を寺にしたものである。法隆寺に所在する聖徳宗の寺院で、山号を法興山といい、開基は聖徳太子であるが、創建の詳細な事情は不明となっている。
金堂は、昭和43年建立の鉄筋コンクリート造り、境内に佇むと尼寺特有の清楚さが流れる。
拡大画像は画像をクリックしてください。
画像上:金堂
画像下:木造菩薩半跏像(国宝)
(平成30年3月8日 探訪)
古寺探訪66ー海龍王寺ー奈良
2018年5月16日 エッセイ
海龍王寺は藤原不比等の邸に建立された。
藤原一族の菩提寺は興福寺であるが、海龍王寺は光明皇后の発願、伝玄昉の開基となっており、興福寺の公寺とちがって邸内に建てられた藤原氏の私寺の位置にある。
養老4年(720年)の不比等の死後、邸宅は娘の光明皇后が相続して皇后宮となり、天平17年(745年)にはこれが宮寺(のちの法華寺)となった。敷地の東北隅に建てられたことから隅寺の別称あって法華寺に隣接していて、当時は知らないが今はひらいて両所出入りができるようになっている。
海の龍とはおどろしい偶像の海生物である。唐の匂いがふんぷんとする、日本の宗教に馴染まない響きがするようだが、真言宗にはこの語句の経があるそうだが凡人には定かでない。
中国唐の時代、文化の交易が盛んに行われ遣唐使の制度が有り仏教はもちろん多様な学問を学び持ち帰ってきた。その論でゆけば、中世の大陸文化は大和の土壌に奇しくも新芽を育てたといえるだろう。ただし近代の大陸ではありえない。
遣唐使として唐に渡り修業した玄昉が帰国途上で暴風に遭い種子島に漂着したさい、船中で海龍王経を一心に唱えて救われたといわれ、海龍王寺の名はこの経文に因んだものといわれている。真言律宗が宗派、本尊十一面観音立像である。春と秋の特別拝観時のみ開帳される。
画像上:金堂
画像中:十一面観音立像
画像下:五重小塔
(平成30年3月8日 探訪)
藤原一族の菩提寺は興福寺であるが、海龍王寺は光明皇后の発願、伝玄昉の開基となっており、興福寺の公寺とちがって邸内に建てられた藤原氏の私寺の位置にある。
養老4年(720年)の不比等の死後、邸宅は娘の光明皇后が相続して皇后宮となり、天平17年(745年)にはこれが宮寺(のちの法華寺)となった。敷地の東北隅に建てられたことから隅寺の別称あって法華寺に隣接していて、当時は知らないが今はひらいて両所出入りができるようになっている。
海の龍とはおどろしい偶像の海生物である。唐の匂いがふんぷんとする、日本の宗教に馴染まない響きがするようだが、真言宗にはこの語句の経があるそうだが凡人には定かでない。
中国唐の時代、文化の交易が盛んに行われ遣唐使の制度が有り仏教はもちろん多様な学問を学び持ち帰ってきた。その論でゆけば、中世の大陸文化は大和の土壌に奇しくも新芽を育てたといえるだろう。ただし近代の大陸ではありえない。
遣唐使として唐に渡り修業した玄昉が帰国途上で暴風に遭い種子島に漂着したさい、船中で海龍王経を一心に唱えて救われたといわれ、海龍王寺の名はこの経文に因んだものといわれている。真言律宗が宗派、本尊十一面観音立像である。春と秋の特別拝観時のみ開帳される。
画像上:金堂
画像中:十一面観音立像
画像下:五重小塔
(平成30年3月8日 探訪)
古寺探訪65-綾部・安国寺③/3
2018年5月3日 エッセイ
室町幕府初代将軍足利尊氏との関りが深い寺院でもある。
綾部安国寺は建長4年(1252)勧修寺重房が上杉姓を賜り、以来、上杉氏の氏寺となっている。
尊氏の母上杉清子は、この地で地蔵菩薩に祈願して尊氏を産んだと伝えられ、足利氏の尊崇を享けるようになった。境内に昇る左に尊氏の産湯に使われた井戸があり、また境内の一隅に尊氏と母清子、妻登子の墓が祀られている。いずれも分骨であろうと思われる。
紅葉の美しい寺としてつとに有名である。
画像上:鐘楼
画像中:足利尊氏 産湯の井戸
画像下:足利墓所 尊氏(中) 母清子(左) (右)妻登子
綾部安国寺は建長4年(1252)勧修寺重房が上杉姓を賜り、以来、上杉氏の氏寺となっている。
尊氏の母上杉清子は、この地で地蔵菩薩に祈願して尊氏を産んだと伝えられ、足利氏の尊崇を享けるようになった。境内に昇る左に尊氏の産湯に使われた井戸があり、また境内の一隅に尊氏と母清子、妻登子の墓が祀られている。いずれも分骨であろうと思われる。
紅葉の美しい寺としてつとに有名である。
画像上:鐘楼
画像中:足利尊氏 産湯の井戸
画像下:足利墓所 尊氏(中) 母清子(左) (右)妻登子
古寺探訪64-綾部・安国寺②
2018年5月1日 エッセイ
京都縦貫自動車道が頭上をかすめて走っており、福知山、舞鶴が近接する京都北部に位置している。安国寺界隈は田園が裾をひろげて、日本の原風景とも懐古の趣がただよっていた。門前にパーキングが無くて離れた田の広地にバスが駐まり、高速道をくぐって門前に歩いた。長い石段が見える。いつもの如く最後尾で広い境内に昇ると正面に藁ぶきの本殿があり、左に方丈等があった。
本尊の、重要文化財の木造釈迦三尊坐像が真近で拝観できたのは幸いであった。
画像上:本堂
画像中、下:重要文化財 木造釈迦三尊坐像
本尊の、重要文化財の木造釈迦三尊坐像が真近で拝観できたのは幸いであった。
画像上:本堂
画像中、下:重要文化財 木造釈迦三尊坐像
古寺探訪63-綾部・安国寺①
2018年4月30日 エッセイ安国寺と名のついた寺院は各地にみられる。宗派も真言宗から臨済宗に多岐にわたっているので縛りのある宗旨ではなく、伝えられるのは南北朝以降の戦死者の霊を弔う寺院であるそうだ。もとは光福寺と称したが後年安国寺となっている。
創建は諸説あり足利尊氏が夢想国師に薦められ、全国に1寺1塔の設置を布れた。寺は安国寺、塔は利生塔との光厳上皇の院宣を享けている。ただし、993年ごろ(正歴4年)臨済宗東福寺派として景徳山と号しての開基と記述があることから、創建年月日について甚だ疑問符されている。
本尊は木造釈迦三尊座像(国の重要文化財)と地蔵菩薩を合せて祀っている。
「・・・丹波国では光福寺が安国寺となり、諸国安国寺の筆頭として、室町幕府も厚い庇護を受け、それ以降、塔頭16、支院28を有する大寺院となった。しかし、江戸中期に至るまでに大半の寺領は押領されて、塔頭、支領は減少したが、広い境内には享保年間(1716~36)建立の本堂、庫裏、方丈をはじめ、開山堂、山門、鐘楼、などが立ち並び、名刹の風格を伝えたいる。本尊の他に国の重要文化財として、木造地蔵菩薩半枷像、絹本墨書天あん和尚入寺山門疏、安国寺文書がある。-歴史探訪クラブよりー」
(平成30年4月12日 探訪)
画像上:山門を正面にした石段
画像中;境内正面にある本堂(仏殿)
画像下:石段
墨 酔1ー山崎徹道氏①-18書展
2018年4月17日 エッセイ
筆跡に作者の意図や文字の構成に妙味がうかがえれば十分書道は楽しめる。作者に失礼を承知で、素人なりに理解させてもらって、書は絵画なのである、と悦に浸っているのである。
上:左・山崎徹道氏 右・友人
中:「遊芸」
下:「観」
上:左・山崎徹道氏 右・友人
中:「遊芸」
下:「観」
古寺探訪62ー西大寺3ー奈良
2018年4月10日 エッセイ
中興の祖は鎌倉時代の僧:叡尊である。90歳で亡くなるまで荒廃していた西大寺の復興に尽くした。日本仏教の腐敗堕落を憂い、戒律の復興にもつとめ今日でいう福祉事業をおこなった。また荒廃著しい諸国の国分寺の再興にも努めている。
真言律宗というのは、真言宗と地元n律宗を合体させたもので真言宗からは独立している。
岡山の西大寺は高野山真言宗別格本山の宗派である。
画像上:東塔跡表示
画像下:中興の祖 叡尊
真言律宗というのは、真言宗と地元n律宗を合体させたもので真言宗からは独立している。
岡山の西大寺は高野山真言宗別格本山の宗派である。
画像上:東塔跡表示
画像下:中興の祖 叡尊
古寺探訪61-西大寺2ー奈良
2018年4月9日 エッセイ
重祚した称徳天皇と弓削道鏡の交錯、称徳天皇の家庭教師のような吉備真備、道鏡が天皇になろうとしたときに義勇を奮った和気清麻呂とその姉の広虫など岡山人が重く関って活躍した時代で、資料や書物をひもとくと歴史の興味はつきない。
横道にそれたついでに私観を述べれば、歴史の上で面白いと想う時代は、一に奈良平安時代、二に応仁の乱時代、三に戦国時代で、四に幕末の革命争乱を挙げる。いずれも朝廷を巻きこんで武士たる権力の蓑を着て権威の笠を被ろうとして興した乱である。
上の画像:本 堂
下の画像:愛染堂
横道にそれたついでに私観を述べれば、歴史の上で面白いと想う時代は、一に奈良平安時代、二に応仁の乱時代、三に戦国時代で、四に幕末の革命争乱を挙げる。いずれも朝廷を巻きこんで武士たる権力の蓑を着て権威の笠を被ろうとして興した乱である。
上の画像:本 堂
下の画像:愛染堂
古寺探訪(古寺素描改)60ー西大寺1ー奈良
2018年4月1日 エッセイ
真言律宗総本山の寺院。創建は天平神護元年というからことのほか古い。山号を勝宝山、院号を四王院、重要文化財僧の釈迦如来を本尊にいただいている。常騰を初代住職として建立、時の孝謙上皇が(のちに称徳天皇)建立に深く関っている。孝謙上皇のとき恵美押勝の乱平定の発願して金銅四天王像の造立を行っている。
西大寺の寺名「西大寺」は「東大寺」に対するものだ.
壮大な寺域と伽藍を擁し、薬師金堂、弥勒金堂、四王堂、十一面堂、東西五重塔が並び南都七大寺のひとつにかぞえられていた。大仏で有名な東大寺の仏教華美はないが、いかにも古寺のたたずまいを保持していた。称徳天皇といえば女性天皇でその庇護を享けるばかりか、公私にわたって天皇を補佐つかさどり、自ら天皇に生り替わろうとした僧・弓削道鏡がいたことが西大寺建立に思想的影響を与えたといわれる。
創建当時の壮大さは、中心に薬師金堂、その背後に弥勒金堂、、東に小塔院、北に食堂院、中心伽藍の西に正倉院、北に政所院、中心伽藍の前は東西2基の五重塔、この東に四王院、西に十一面堂院、その南には西南角院があってこの伽藍配置にもみられるそうだ。
しかし平安時代に入って衰退し、たび重なる火災台風に遭いこれらの多くの堂塔が失い境内にある祭壇や礎石が往時の投影を窺うことができる。現存の堂宇は江戸時代のものばかりである。
その末に藤原一族の菩提寺である興福寺の支配下に入っている。
西大寺の寺名「西大寺」は「東大寺」に対するものだ.
壮大な寺域と伽藍を擁し、薬師金堂、弥勒金堂、四王堂、十一面堂、東西五重塔が並び南都七大寺のひとつにかぞえられていた。大仏で有名な東大寺の仏教華美はないが、いかにも古寺のたたずまいを保持していた。称徳天皇といえば女性天皇でその庇護を享けるばかりか、公私にわたって天皇を補佐つかさどり、自ら天皇に生り替わろうとした僧・弓削道鏡がいたことが西大寺建立に思想的影響を与えたといわれる。
創建当時の壮大さは、中心に薬師金堂、その背後に弥勒金堂、、東に小塔院、北に食堂院、中心伽藍の西に正倉院、北に政所院、中心伽藍の前は東西2基の五重塔、この東に四王院、西に十一面堂院、その南には西南角院があってこの伽藍配置にもみられるそうだ。
しかし平安時代に入って衰退し、たび重なる火災台風に遭いこれらの多くの堂塔が失い境内にある祭壇や礎石が往時の投影を窺うことができる。現存の堂宇は江戸時代のものばかりである。
その末に藤原一族の菩提寺である興福寺の支配下に入っている。
暦上では春に両足ふみこんだ季節だが、実際にはようやく片足をふみいれたという感覚である。
短い温かさに少し膨らんだ心身だが、翌日は寒冷の吹き込みに眉のくもる按配である。
まったくもつておかしな気象には悩ませられる。
北の寒冷前線と南からの低気圧に挟まれて列島おろか世界に異常な現象をもたらしている。
重苦しい空から雨滴が落ち始めた。
久しぶりの「歴史探訪クラブ」バスツアーなので、雨降りはご勘弁ねがいたい。幸い高速を東にいくに連れ雨はあがってきた。
短い温かさに少し膨らんだ心身だが、翌日は寒冷の吹き込みに眉のくもる按配である。
まったくもつておかしな気象には悩ませられる。
北の寒冷前線と南からの低気圧に挟まれて列島おろか世界に異常な現象をもたらしている。
重苦しい空から雨滴が落ち始めた。
久しぶりの「歴史探訪クラブ」バスツアーなので、雨降りはご勘弁ねがいたい。幸い高速を東にいくに連れ雨はあがってきた。
夏がくれば冬を想い、冬がくれば夏を焦がれる。
一年を通すと「温かい自然」がいかに少ないか実感する。
昔は春夏秋冬のバランスが良好の配分に成り立っていたように思うが、近年そのつり合いが偏向した気候で、期間が長くなった按配である。いずれ地球規模で季節の定義が変わってくるかも知れない。人間の持つ傲慢のなせる業となると雪崩のような極化への恐怖が、ないでもない。
そんな酷寒でも植物は健気にリズムを追っている。
庭のボケに赤い蕾が膨らんできた。
春近しの想いに、硬くなった心身が、ホッと和む。
一年を通すと「温かい自然」がいかに少ないか実感する。
昔は春夏秋冬のバランスが良好の配分に成り立っていたように思うが、近年そのつり合いが偏向した気候で、期間が長くなった按配である。いずれ地球規模で季節の定義が変わってくるかも知れない。人間の持つ傲慢のなせる業となると雪崩のような極化への恐怖が、ないでもない。
そんな酷寒でも植物は健気にリズムを追っている。
庭のボケに赤い蕾が膨らんできた。
春近しの想いに、硬くなった心身が、ホッと和む。
古寺素描21-能勢妙見山②完
2018年1月3日 エッセイ
能勢妙見山は真如寺(関西身延)の境外仏堂といわれ、境外仏堂とは飛地境内にある仏堂の意味合いの位にあることだが、参詣者の多寡からみると本寺よりはるかに賑わっているらしい。江戸時代の戯作者・近松門左衛門も熱心な信者とのことで花柳界、芸能界に信仰があった。それも、妙なる姿=美しい姿という寺名から流れたものらしい。
歴史をめくるともっと面白い。ここはクラブの資料から引用しておきたい。
『・・山頂には行基の建立といわれる為樂山大空寺があったが、鎌倉時代に入ると源頼国(源頼光の長男)を祖とする能勢氏が領主となり、この地に妙見菩薩を祀ったとされる。安土桃山時代に領主であった能勢頼次が、本能寺の変で明智光秀に加担したために領土を失ったが、徳川家康の家臣となり関ヶ原の戦いで活躍したことにより、能勢の地を領地として宛がわれ、旗本として能勢氏を再興した。頼次は日蓮宗の日乾(後に身延山久遠寺二十一世)に帰依し、自らが開いた真如寺の開山とした。慶長8年(1603年)には日乾の手によって新たな妙見菩薩が彫られ、大空寺の址である所に仏堂を建立して祀った。これが現在の能勢妙見山である。』
権力と宗教が表裏で張り合わせになっている史実を、隙間からうかがうことができる。(権威は権力より上段にある)
脆弱の脚に鞭うって集団の最後尾をよろよろと降りた。もっともこんな天候だから、他の参詣人には出会うことはなかった。
歴史をめくるともっと面白い。ここはクラブの資料から引用しておきたい。
『・・山頂には行基の建立といわれる為樂山大空寺があったが、鎌倉時代に入ると源頼国(源頼光の長男)を祖とする能勢氏が領主となり、この地に妙見菩薩を祀ったとされる。安土桃山時代に領主であった能勢頼次が、本能寺の変で明智光秀に加担したために領土を失ったが、徳川家康の家臣となり関ヶ原の戦いで活躍したことにより、能勢の地を領地として宛がわれ、旗本として能勢氏を再興した。頼次は日蓮宗の日乾(後に身延山久遠寺二十一世)に帰依し、自らが開いた真如寺の開山とした。慶長8年(1603年)には日乾の手によって新たな妙見菩薩が彫られ、大空寺の址である所に仏堂を建立して祀った。これが現在の能勢妙見山である。』
権力と宗教が表裏で張り合わせになっている史実を、隙間からうかがうことができる。(権威は権力より上段にある)
脆弱の脚に鞭うって集団の最後尾をよろよろと降りた。もっともこんな天候だから、他の参詣人には出会うことはなかった。
古寺素描20-能勢妙見山①
2018年1月2日 エッセイ
日蓮宗の関西随一の霊場で、正式名を無漏山真如寺境外仏堂能勢妙見山と、なんとも長い寺名である。大阪府豊能郡能勢町の妙見山(標高622メートル)の山頂にあり、霊場だけに全山鬱蒼とした森林にかこまれた雰囲気は、薄靄に目隠しされ葉を伝う滴の妖気に重たく滅入った。
境内の売店からさらに石段があらわれて登段を断念、方向転換したとき同じ気分の女性をみつけ一緒になった。すると売店の人がよってきて石段のない迂回路を教えてくださり、ならばそちらを登ろうとくだんの女性と同行することになった。地道の鬱蒼とした陽のささない小径を、葉溜まりを踏むと水が滲みでるのを避けながら登りつめる。突き当たりは三叉路、左側の傾斜道に大きな鳥居が見え、ようやく頂上の施設にたどりついたとみえ、安堵感が湧いた。鳥居はかっての神仏習合の名残である。それが靄のかいまに点在し屋の輪郭をぼやけさしている。境内右手の施設は神社でみられる社務所の形態、左手は能勢妙見堂や神馬の銅像、はては日蓮上人の銅像があって神仏混淆そのものだが今は仏教だけの霊場
になっている。妙な趣はさらにプロネタニュムのような超近代的な建物が境内北側にあるということだ。
境内の売店からさらに石段があらわれて登段を断念、方向転換したとき同じ気分の女性をみつけ一緒になった。すると売店の人がよってきて石段のない迂回路を教えてくださり、ならばそちらを登ろうとくだんの女性と同行することになった。地道の鬱蒼とした陽のささない小径を、葉溜まりを踏むと水が滲みでるのを避けながら登りつめる。突き当たりは三叉路、左側の傾斜道に大きな鳥居が見え、ようやく頂上の施設にたどりついたとみえ、安堵感が湧いた。鳥居はかっての神仏習合の名残である。それが靄のかいまに点在し屋の輪郭をぼやけさしている。境内右手の施設は神社でみられる社務所の形態、左手は能勢妙見堂や神馬の銅像、はては日蓮上人の銅像があって神仏混淆そのものだが今は仏教だけの霊場
になっている。妙な趣はさらにプロネタニュムのような超近代的な建物が境内北側にあるということだ。
古寺素描59-応頂山勝尾寺②完
2017年12月9日 エッセイ
神亀4年(727)開基と伝えられる西国33ヶ所第23番の札所である。本尊は十一面千手観世音菩薩である。寺号は「かつおじ」「かちおじ」などとも読まれる。境内は蓑面山の東に接し、開城皇子陵墓、光明院勝応寺陵(南北朝時代北朝第2代光明天皇陵墓)などの他、本堂、多宝塔、二階堂、荒神堂などがある。近年建て替えられた本堂や楼門以外の諸堂の多くは豊臣秀頼の命により片桐且元が修築したものである。
寺宝にはいずれも国重要文化財の法華経巻第四、木造薬師如来坐像及び両脇侍像、勝尾寺旧境内膀示八天石蔵(寺領を明示し、土地を巡る争いを避けるために寺の周囲8ヶ所に設置したもの)からの出土品銅像四天王・四大明王像8体などがある。
・・・・「歴史探訪クラブ」の資料から引用・・・・・
画像上:多宝塔
画像中:太子堂
画像下:弁財天
寺宝にはいずれも国重要文化財の法華経巻第四、木造薬師如来坐像及び両脇侍像、勝尾寺旧境内膀示八天石蔵(寺領を明示し、土地を巡る争いを避けるために寺の周囲8ヶ所に設置したもの)からの出土品銅像四天王・四大明王像8体などがある。
・・・・「歴史探訪クラブ」の資料から引用・・・・・
画像上:多宝塔
画像中:太子堂
画像下:弁財天
古寺素描58ー応頂山勝尾寺①
2017年12月1日 エッセイ
大阪府箕面市にある高野山真言宗の寺院。門内から山門までの境内は新装整備した庭園の雰囲気が漂う。
多くの伽藍は山の傾斜面に張り付いて見え、当寺も同様、ちかずくと弁天池の境界あたりから長い石段がのびており、腰がひけて石段を数えて昇る始末、左に小さなダルマがずらり並んだ石灯篭に笑われているようだった。
ダルマがいたるところにあって緑陰の陰に様々な笑みをなげかけていた。
「勝運」の寺でもある。
勝尾寺に縁があるのは浄土宗の法然上人。
法然上人はわが岡山の出目で生誕した誕生寺も近隣にある。その関りで法然配流の事件を少し追ってみると、当時の後鳥羽上皇が熊野詣で京都に不在になり、留守中に、院の女房たちが法然門下で唱導を能くする遵西・住蓮のひらいた東山鹿ヶ谷草庵(京都市左京区)での念仏法会に参加しさらに出家して尼僧となったという事件であった。
この事件に関連して、女房たちは遵西・住蓮と密通したという噂が流れ、それが上皇の大きな怒りを買ったのである。法然は還俗させられ、「藤井元彦」を名前として讃岐国に流罪となった。承元元年(1207年)12月に赦免されて讃岐国から戻った法然が摂津国豊島郡(現箕面市)の勝尾寺に承元4年(1210年)3月21日まで滞在した。
亨年80歳の由。
画像上:門前碑
画像中:山門
画像下:小雨ふる石段
多くの伽藍は山の傾斜面に張り付いて見え、当寺も同様、ちかずくと弁天池の境界あたりから長い石段がのびており、腰がひけて石段を数えて昇る始末、左に小さなダルマがずらり並んだ石灯篭に笑われているようだった。
ダルマがいたるところにあって緑陰の陰に様々な笑みをなげかけていた。
「勝運」の寺でもある。
勝尾寺に縁があるのは浄土宗の法然上人。
法然上人はわが岡山の出目で生誕した誕生寺も近隣にある。その関りで法然配流の事件を少し追ってみると、当時の後鳥羽上皇が熊野詣で京都に不在になり、留守中に、院の女房たちが法然門下で唱導を能くする遵西・住蓮のひらいた東山鹿ヶ谷草庵(京都市左京区)での念仏法会に参加しさらに出家して尼僧となったという事件であった。
この事件に関連して、女房たちは遵西・住蓮と密通したという噂が流れ、それが上皇の大きな怒りを買ったのである。法然は還俗させられ、「藤井元彦」を名前として讃岐国に流罪となった。承元元年(1207年)12月に赦免されて讃岐国から戻った法然が摂津国豊島郡(現箕面市)の勝尾寺に承元4年(1210年)3月21日まで滞在した。
亨年80歳の由。
画像上:門前碑
画像中:山門
画像下:小雨ふる石段
古寺素描57-法隆寺②完
2017年11月20日 エッセイ
先ず外郭を探索し、やおら境内の伽藍を観て歩くのがいいと想う。
しかしそれには一日の時間ぐらいではとても叶わない。まして時間を拘束されて観る分は衣をかすめ春風にたゆたうような頼りない気分しか残らない。欲の虚しさだけである。
「柿食えば鐘がなるなり法隆寺」
歌人・正岡子規の有名な俳句である。池の側に歌碑が建っている。
子規は柿が好物で小鉢一杯の柿を一度に食べたとか、ただ甘柿ではなく渋を抜いたものが好きだったらしく、その経緯をものの本で読んだことがある。そのうえ、句作したときは持病で入院していたという。
画像:正岡子規 歌碑
しかしそれには一日の時間ぐらいではとても叶わない。まして時間を拘束されて観る分は衣をかすめ春風にたゆたうような頼りない気分しか残らない。欲の虚しさだけである。
「柿食えば鐘がなるなり法隆寺」
歌人・正岡子規の有名な俳句である。池の側に歌碑が建っている。
子規は柿が好物で小鉢一杯の柿を一度に食べたとか、ただ甘柿ではなく渋を抜いたものが好きだったらしく、その経緯をものの本で読んだことがある。そのうえ、句作したときは持病で入院していたという。
画像:正岡子規 歌碑
古寺素描56-法隆寺①
2017年11月12日 エッセイ
法隆寺は日本で一番古い寺院で斑鳩の里に建立。
古代宗教美術の宝庫とされていて、東大寺や興福寺の県都に近い寺院より東大阪に近い北部に位置し奈良県生駒郡斑鳩町にある寺院、広大な寺域(境内の広さは約18万7千平方メートル)をしめている。
聖徳宗の総本山で別名は斑鳩寺ともいう。
創建は7世紀は推古15年(607年)とされ、古代寺院の姿を現在に伝える仏教施設であり、聖徳太子ゆかりの寺院である。金堂、五重塔を中心とする西院伽藍と、夢殿を中心とした東院伽藍に分けられる。西院伽藍は現存する世界最古の木造建築物群である。
画像上:前景
画像中:金堂
画像下:五重塔
古代宗教美術の宝庫とされていて、東大寺や興福寺の県都に近い寺院より東大阪に近い北部に位置し奈良県生駒郡斑鳩町にある寺院、広大な寺域(境内の広さは約18万7千平方メートル)をしめている。
聖徳宗の総本山で別名は斑鳩寺ともいう。
創建は7世紀は推古15年(607年)とされ、古代寺院の姿を現在に伝える仏教施設であり、聖徳太子ゆかりの寺院である。金堂、五重塔を中心とする西院伽藍と、夢殿を中心とした東院伽藍に分けられる。西院伽藍は現存する世界最古の木造建築物群である。
画像上:前景
画像中:金堂
画像下:五重塔